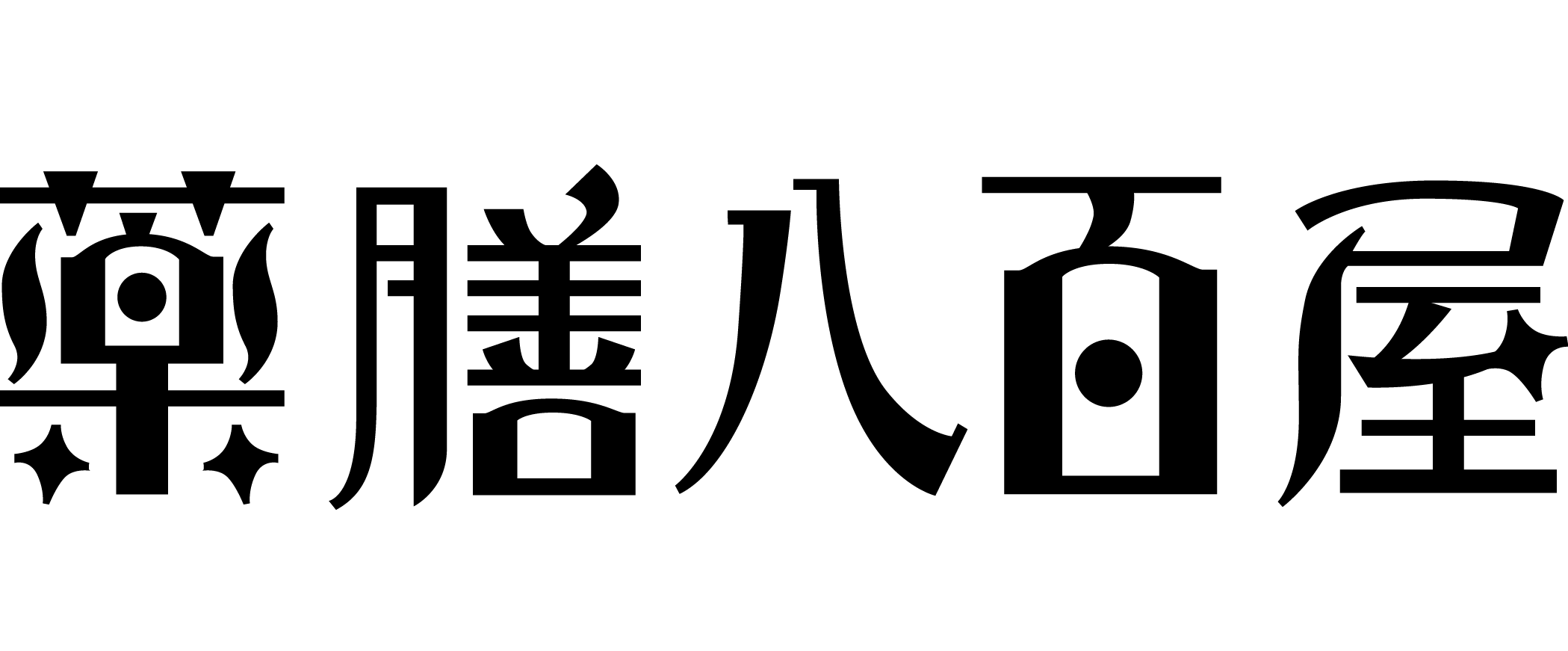乾燥させると解毒作用は失効
平地のやや湿った場所にどこにでも見ることができます。独特の臭気があり、毒が入っていそう…ということで、和名は「毒溜み」「毒嬌み」と言われています。
十種の効能があるから十薬と言われているのは俗説です。
乾燥させる解毒作用が失効するので、生のまま外用薬として利用することがあります。
新鮮な生の葉を火であぶって柔らかくしたものを腫物の患部にあてて膿を吸いだす治療方法は昔から行われており、葉の汁を湿疹、水虫、かぶれなどに用いることもあります。
今日では、ドクダミ茶として、べんぴ高血圧、皮膚炎の体質改善に利用されています。
漢方では、肺炎や気管支炎、、膀胱炎、腫物、痔などに用います。