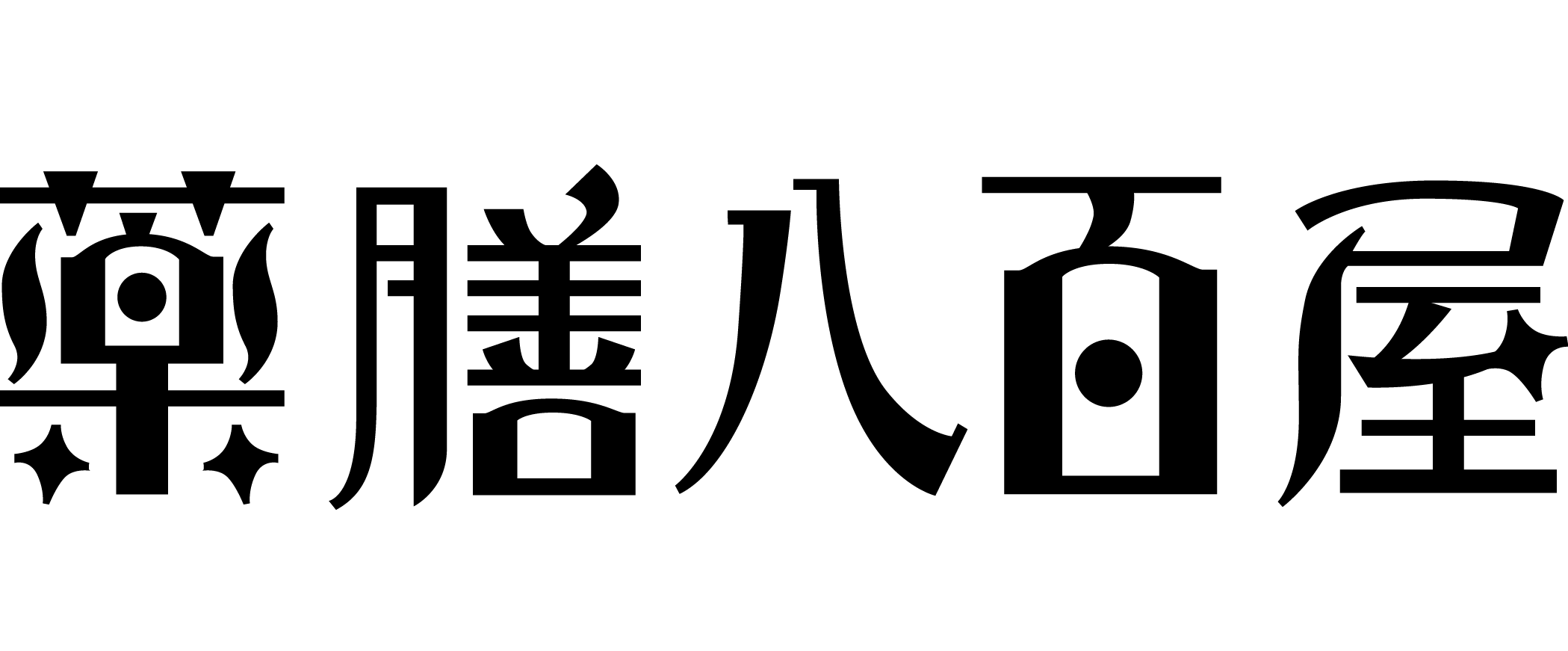日本には9世紀前後に渡来したと推定されています。江戸中期に農村で果樹として栽培されるようになり、幕末なって清国から長崎に伝えられて以降、 日本各地に普及しました。
薬理作用として抗炎症作用や抗菌作用が知られています。
漢方では止咳、止嘔の効能があり、咳や痰、鼻血、嘔吐用います。
民間ではアセモや湿疹を治療する浴湯料として使用したり、枇杷の葉(温圧)療法という
民間療法もある。
こちらは、あぶったビワの葉を置いた上から加熱するという方法で、難病や癌にも効果が
あると言われています。