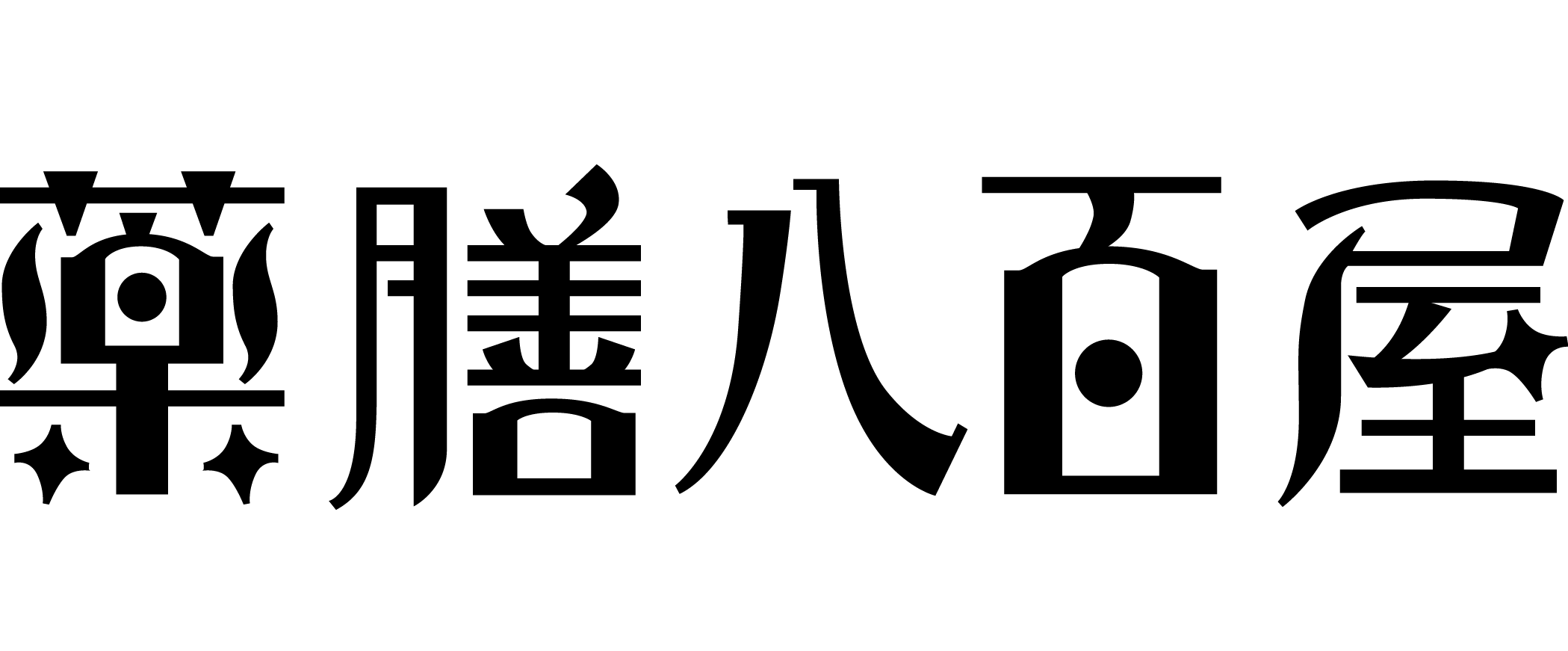シソやチリメンジソジソの葉を用いる。シソの種子は紫蘇子、茎は紫蘇梗と言い、日本でも
古くから用いられ、香りが強いものほど良品とされています。
アントシアン系の赤い色素シアニンの有無によって赤シソと青シソに分けられ、青シソは
大葉とも言い刺身のつまや薬味に、赤シソの葉は梅干しの着色に利用されています。
ちなみに、梅とシソを漬けた梅干しは日本特有の保存食です。
蘇葉の発汗作用は麻黄や桂皮に比べると弱いですが、理気作用により胸の痞えや悪心、
嘔吐を改善する作用もあり、胃腸型の感冒によく使用されます。
また、蘇葉の理気作用には食欲不振や姙娠悪阻にも効果があります。
刺身のつまに青シソが添えられているのは、魚介類による中毒や蕁麻疹にも効果があるため
と言われています。
近年は、夏バテ防止、食欲促進も兼ねて、紫蘇ジュースを作る方も増えてきました。